一般治療
- HOME
- 一般治療
むし歯の原因と対策
むし歯は“慢性疾患”のひとつです。だからこそ、予防と生活習慣の見直しが重要です。
むし歯は一度できてしまうと自然に治ることはなく、進行すれば歯を失う原因にもなります。けれど、正しい知識と少しの意識で、むし歯は確実に予防することができます。
むし歯ができるメカニズム
〜 カイスの4要素 〜
むし歯は、次の4つの条件がそろうことで発生します。
細菌(ミュータンス菌など)
口の中には多くの細菌が存在していますが、中でも「ミュータンス菌」は糖をエネルギーにして酸を出し、歯を溶かす原因菌の代表です。
糖質(主に砂糖)
お菓子・ジュース・菓子パン・スポーツドリンクなどに含まれる糖分は、むし歯菌のエサになります。食べる回数や時間帯がむし歯のリスクに影響します。
歯の質(エナメル質の強さ・唾液の力)
歯の表面が強く、唾液の量や質が良いとむし歯になりにくくなります。唾液には“酸を中和する”・“再石灰化を助ける”という大切な働きがあります。
時間(酸にさらされる時間)
間食が多かったり、口の中がダラダラと酸性に保たれていると、歯が溶けるリスクが高まります。これが「ダラダラ食べ」が良くない理由です。
むし歯予防の具体的な方法

正しい歯みがき習慣
- 1日2回以上、特に就寝前の丁寧な歯みがきは必須です。
- 歯ブラシに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシも活用しましょう。
- 力を入れすぎず、磨き残しやすい部分を意識することがポイントです。

食生活の見直し
- 「何を食べるか」よりも「どう食べるか」が大事です。
- 間食は時間を決めて、口の中を中性に戻す時間を作るようにしましょう。
- 甘いものを食べたあとは、うがいや水分摂取も予防に効果的です。
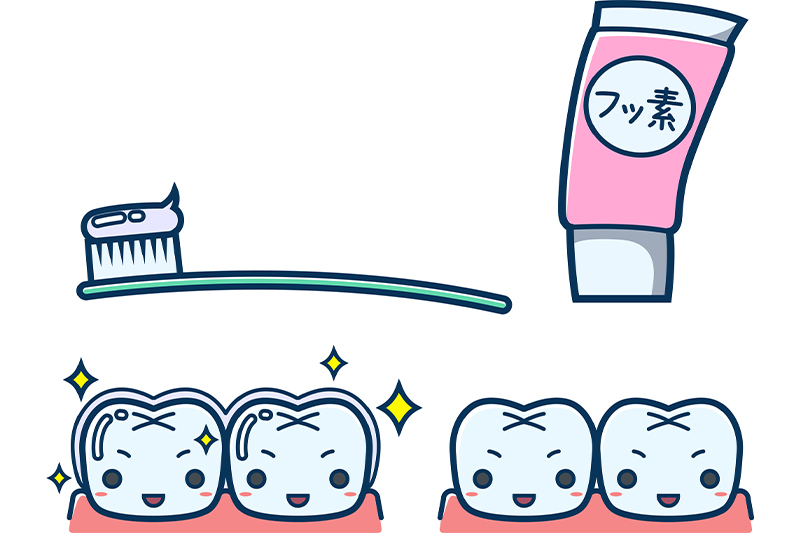
フッ化物の活用
- フッ化物配合の歯みがき剤を使うことで、歯の再石灰化を促し、むし歯の初期段階を修復することも可能です。
- 定期的なフッ化物塗布(特にリスクの高い方)も効果的です。

唾液の働きを高める
- しっかり噛んで食べることは、唾液の分泌を促進し、むし歯予防に直結します。
- 口呼吸やストレス、薬の副作用で唾液が減ることもあるため、生活全体の見直しも大切です。
唾液は「魔法の水」
むし歯や歯周病から歯を守る、あなたの味方です。私たちの口の中にある「唾液」は、実は歯科の世界では**“魔法の水”**と呼ばれるほど、たくさんの素晴らしい働きをしています。
唾液の4つの魔法の力
① 酸を中和する
食後や甘いものを食べた直後、口の中は酸性に傾きます。唾液はこの酸を中和し、歯が溶けるのを防ぎます。
② 再石灰化を促す
カルシウムやリンを歯の表面に届け、酸で溶けかけた部分を修復します。
③ 自浄・抗菌作用
食べカスや細菌を洗い流し、細菌の増殖を抑えます。
④ 傷を癒やす
粘膜を保護し、口内炎などの傷の治りも早める働きがあります。
よく噛むことが唾液を増やします

唾液の分泌は噛む回数によって大きく変わります。現代人は食事が軟らかくなり、噛む回数が減りがちですが、一口30回を目安にしっかり噛むことが理想です。
噛むことで…
- 唾液がたっぷり出る
- 消化がよくなる
- 満腹感が得られ、食べすぎ防止に
- 顎の筋肉が鍛えられる
といった全身の健康にも良い効果があります。
口呼吸は唾液の働きを妨げます

普段、無意識に「口で呼吸している」ことはありませんか?
口呼吸は、唾液が蒸発しやすくなるため、以下のような問題を引き起こします。
- 口の中が乾燥して細菌が繁殖しやすくなる
- 唾液の「自浄作用」「抗菌作用」が低下
- むし歯・歯周病・口臭のリスクが増加
- のどの粘膜も乾燥し、風邪やウイルスにも弱くなる
日中はもちろん、寝ている間の口呼吸(いびき・口の渇き)にも注意が必要です。
当院の取り組み
~むし歯にならないために~

祁答院歯科クリニックでは、治療だけでなく「これ以上むし歯を増やさないために、どうすればいいか」という視点からもサポートを行っています。
- 歯みがきや生活習慣の見直しを含めた予防プログラムの提案
- 患者さんごとのリスク評価(むし歯のなりやすさのチェック)
- フッ化物やシーラント処置など、予防処置の実施
「歯医者は痛くなってから行くところ」から、「健康を守るために行くところ」へ変化してきています。
